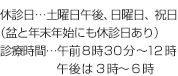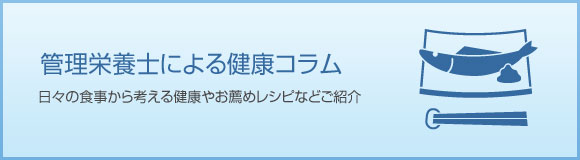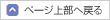最近久しぶりに体重計に乗ったら、体重が…。体重測定は毎日したほうがいいですね。気づいたときには、あれ??っとなってしまいます。毎日測定していれば、今日はこれだけ増えた、減ったがわかるので、私も毎日体重を量っていかなきゃいけないなあと思わされました…。今月は脂質異常症についてです。
脂質異常症とは、血液中の脂質が高値または、異常値を示す状態を言います。血液中の脂質が増えても、体は痛くもかゆくもありません。体調の変化もないので、なかなか自分では気づくことが出来ません。なので、「脂質異常症ですよ!!」といわれてもピンとこずに放置してしまうことも…。放置してしまった脂質異常症は、どんどん血液中の脂質が多くなってどろどろ血液になり、血管の壁にぺたぺたと脂質がこびりついて、固まっていきます。これが動脈硬化です。動脈硬化でも特に体調に変化はなく、これまた放置してしまうと、欠陥にこびりついた脂質がどんどん増えてついには、血管がつまって破裂してしまいます。これが心筋梗塞や脳梗塞の原因になってはじめて脂質異常症の怖さを知ります。
脂質異常症の診断基準
高LDLコレステロール血症 140mg/dl以上
低HDLコレステロール血症 40mg/dl未満
高トリグリセライド血症 150mg/dl以上
(中性脂肪)
脂質異常症を予防するために食事で気をつけることは…??
☆ 適正な体重を維持するために、エネルギーのとりすぎに気をつけましょう。
エネルギーの摂り過ぎ(食べ過ぎ)は、中性脂肪の増加につながっていきます。
☆ 食物繊維を積極的にとりましょう。
食物繊維は体内の余分なコレステロールを体外へ排出してくれる働きがあります。食物繊維がたくさん含まれる野菜や海藻類やきのこ類を積極的に食べましょう。
☆ コレステロールが多く含まれる食品は控えるようにしましょう。
体内のコレステロールの2割~3割が食事から摂取したコレステロールで、後の7~8割は体内で合成されたコレステロールです。コレステロールを多く含む食品を控えるに越したことはないのです。
コレステロールを多く含む食品
するめいか・レバー・たらこ・卵・うなぎの蒲焼・ししゃもなど
☆ 飽和脂肪酸を多く含む食品を控える。
飽和脂肪酸はコレステロールを上げるとされています。コレステロールを含まなくても、飽和脂肪酸を含む食品でコレステロールを上げてしまいます。
飽和脂肪酸を多く含む食品
牛や豚の脂身・バター・牛乳・チョコレート・ショートケーキなど。
☆ 糖質の摂りすぎに注意!!
糖質の摂りすぎは中性脂肪の増加につながります。甘いものの食べすぎには注意です。あわせて果物の食べすぎにも注意です。
今月の献立
小松菜と豚肉の炒め物
(材料) 一人分 269kcal 塩分0.9g
小松菜 100g
豚ももスライス 70g
しょうゆ 小さじ1
酒 小さじ1
しょうが 1g 調味料
にんにく 1g
砂糖 小さじ1/2
ごま油 大さじ1
塩・こしょう 少々
① 豚ももスライスは食べやすい一口大の大きさに切って調味料で漬け込んでおく。
② 小松菜を食べやすい大きさに切り、茎の部分と葉の部分に分けておく。
③ フライパンにごま油を入れて①を炒めて取り出し、そのまま②の茎部分を少し炒めてから、葉の部分を炒める。
④ 最後に取り出した肉をフライパンに戻し、お好みで塩・コショウを入れて味を整えたら出来上がり。
かぶのスープ
(材料) 一人分 35kcal 塩分 0.8g
かぶ 30g
ねぎ 5g
卵 1/4個
中華だし 1g
しょうゆ 小さじ1/3 A
塩 少々
水 200ml
片栗粉 1.5g
① かぶは一口大に切り、ねぎは小口きりにしておく。
② Aとかぶを煮立たせ、かぶに火が通ったら水で溶いた片栗粉を入れかき混ぜたら、そのままかき混ぜながら溶き卵を入れる
③ 最後にねぎを入れたら出来上がり。
参考文献
栄養と料理 2004年 3月
厚生労働省ホームページ 脂質異常症